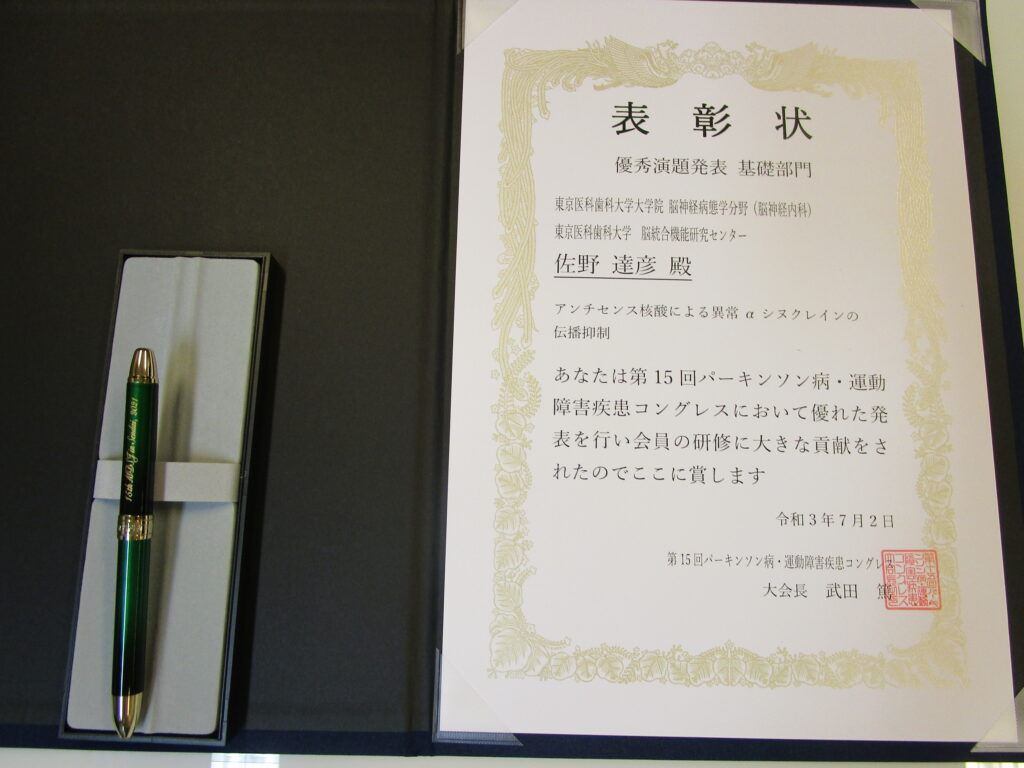西李依子先生、大谷木正貴先生と永田哲也先生はDNA/RNAヘテロ核酸の全身投与(静脈内・皮下投与)により、神経免疫疾患の中枢神経系において活性化されるミクログリア・中枢神経浸潤マクロファージの内在性遺伝子を制御することを証明しました。ヘテロ核酸の送達機構としてマクロファージスカベンジャーレセプター1が関与している事を発見しました。さらに、多発性硬化症モデルの実験的自己免疫性脳脊髄炎マウス(EAEマウス)でミクログリア・マクロファージ上に発現し神経炎症の促進に関与するCD40遺伝子を標的とするヘテロ核酸をEAEマウスに皮下投与すると、CD40の発現が抑制され、臨床スコアが有意に軽症化するこ
とを示しました。この研究結果はMolecular Therapy(IF=11.454)に掲載され、医科歯科大学からプレスリリースしました。
https://www.tmd.ac.jp/press-release/20220401-1/
活性化ミクログリア・中枢神経浸潤マクロファージを制御できれば、神経免疫疾患のみならず神経変性疾患など広範な疾患を治療対象として応用することが期待できます。
横田隆徳

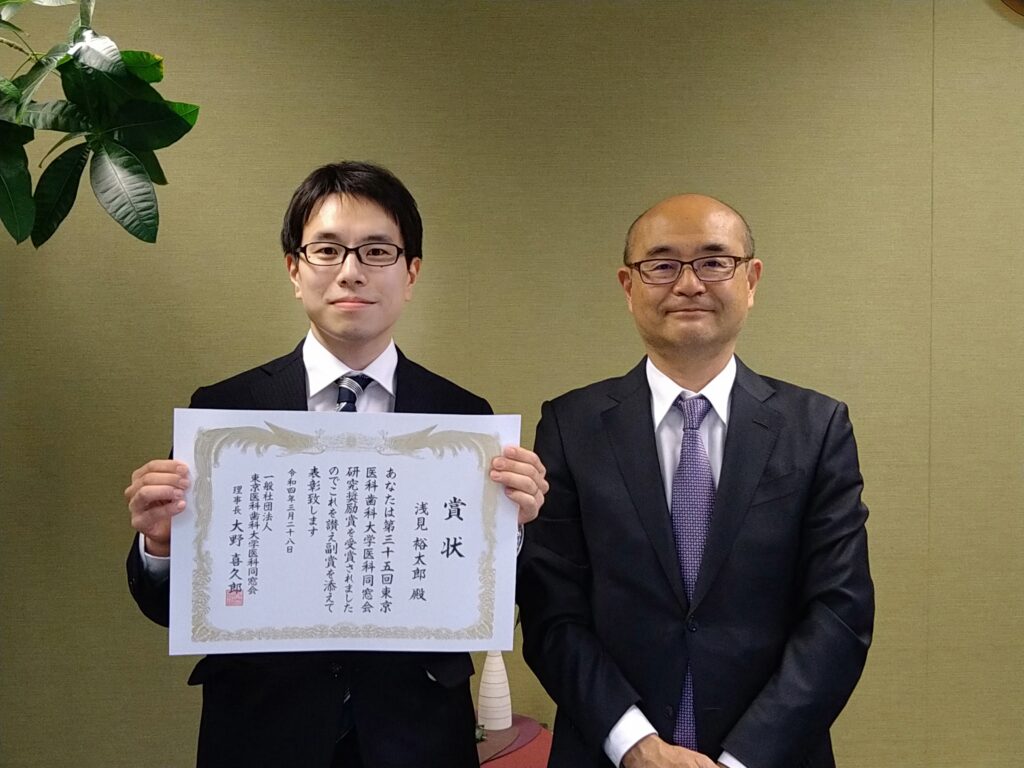
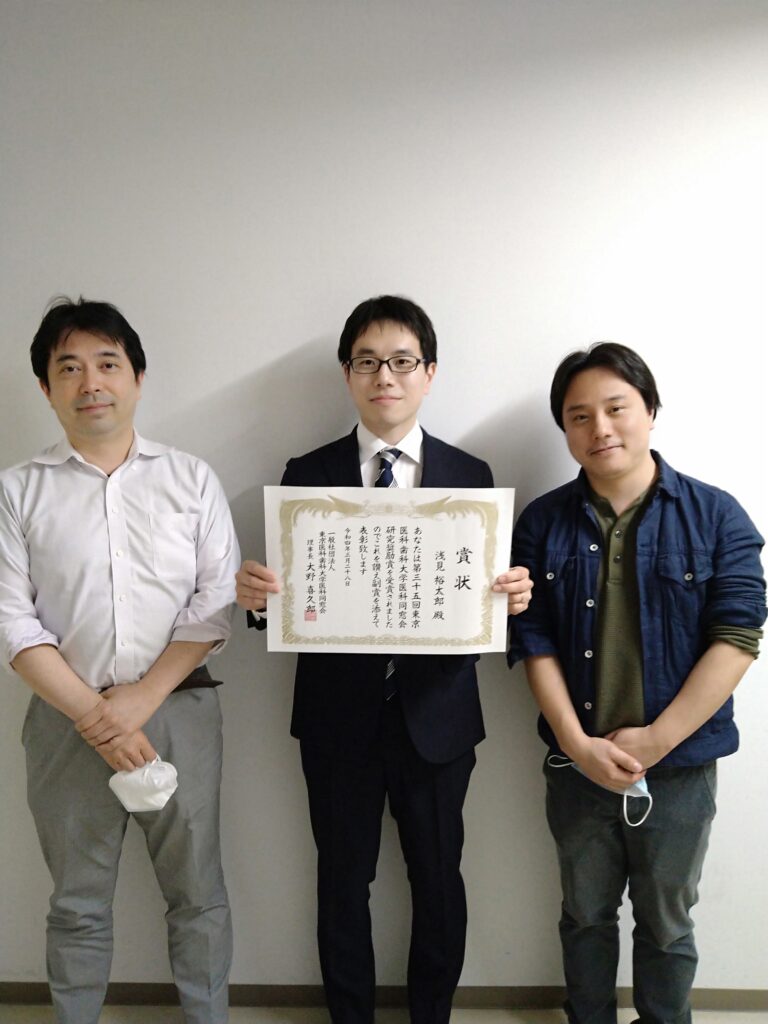
_ページ_1-2-724x1024.jpg)
_ページ_2-1-724x1024.jpg)



-1-775x1024.jpg)